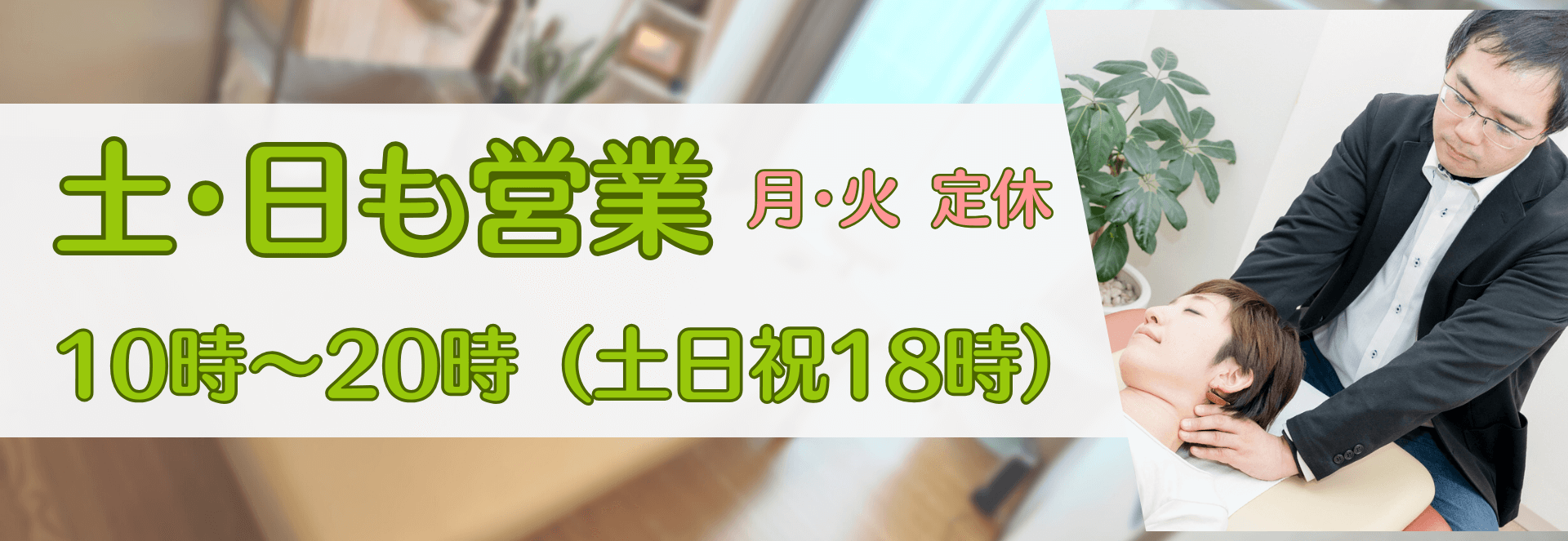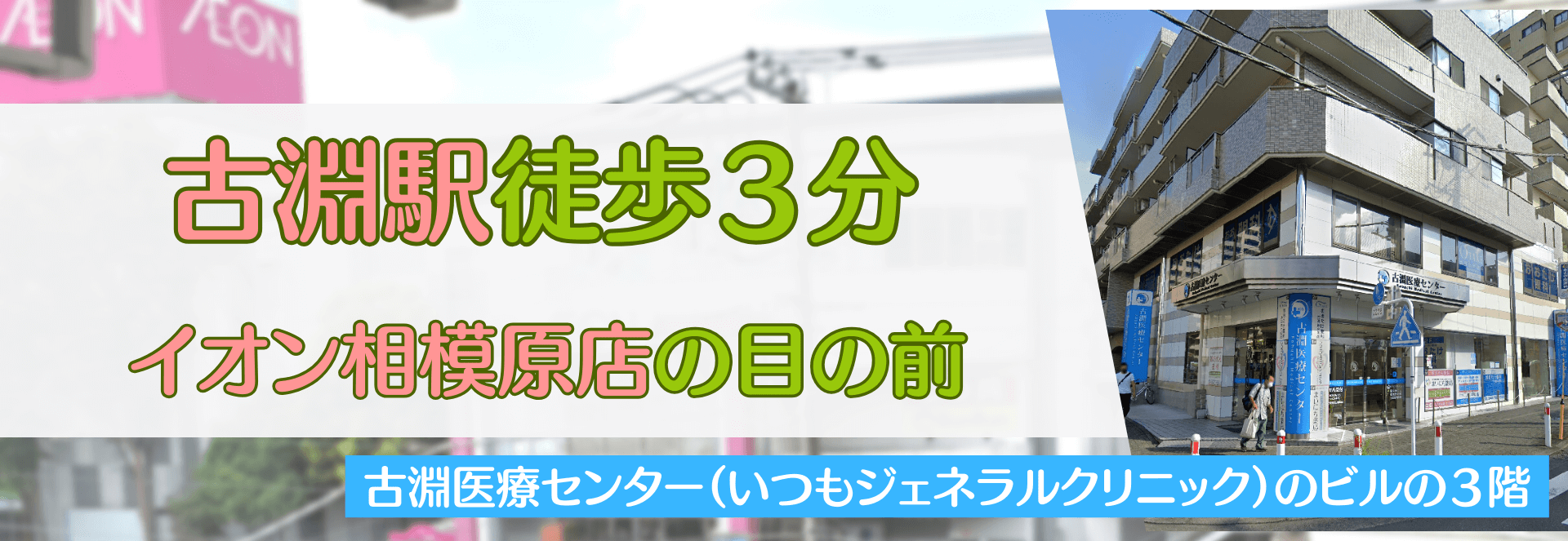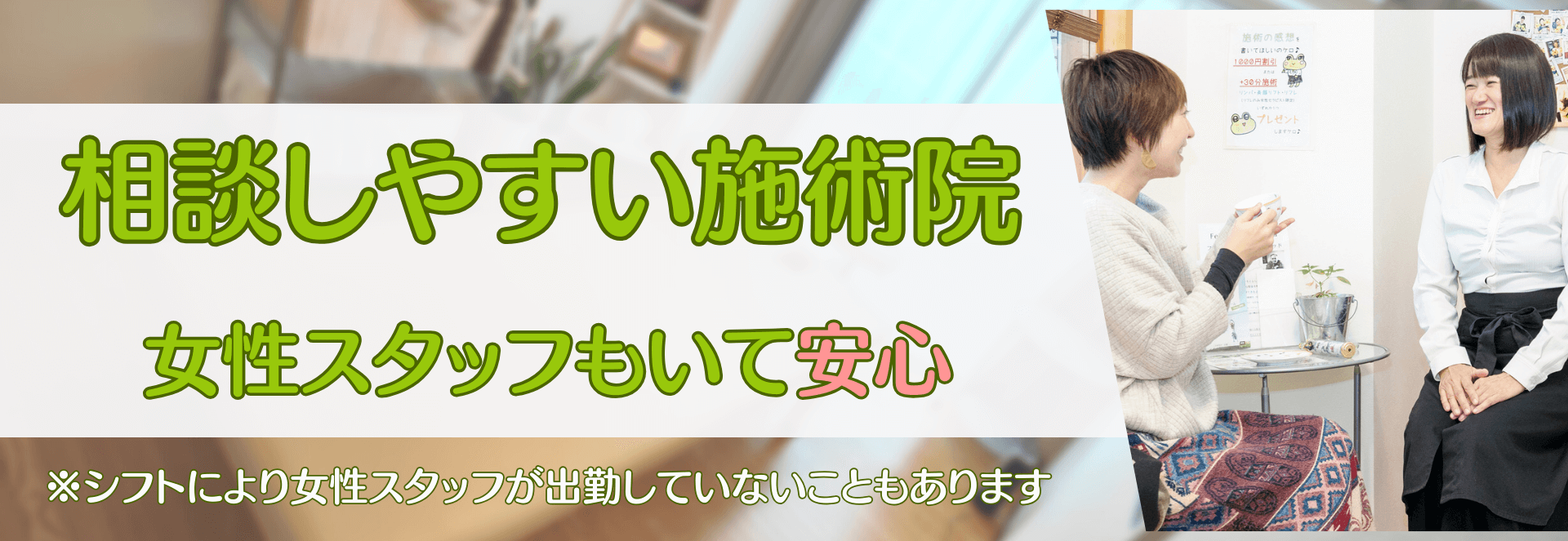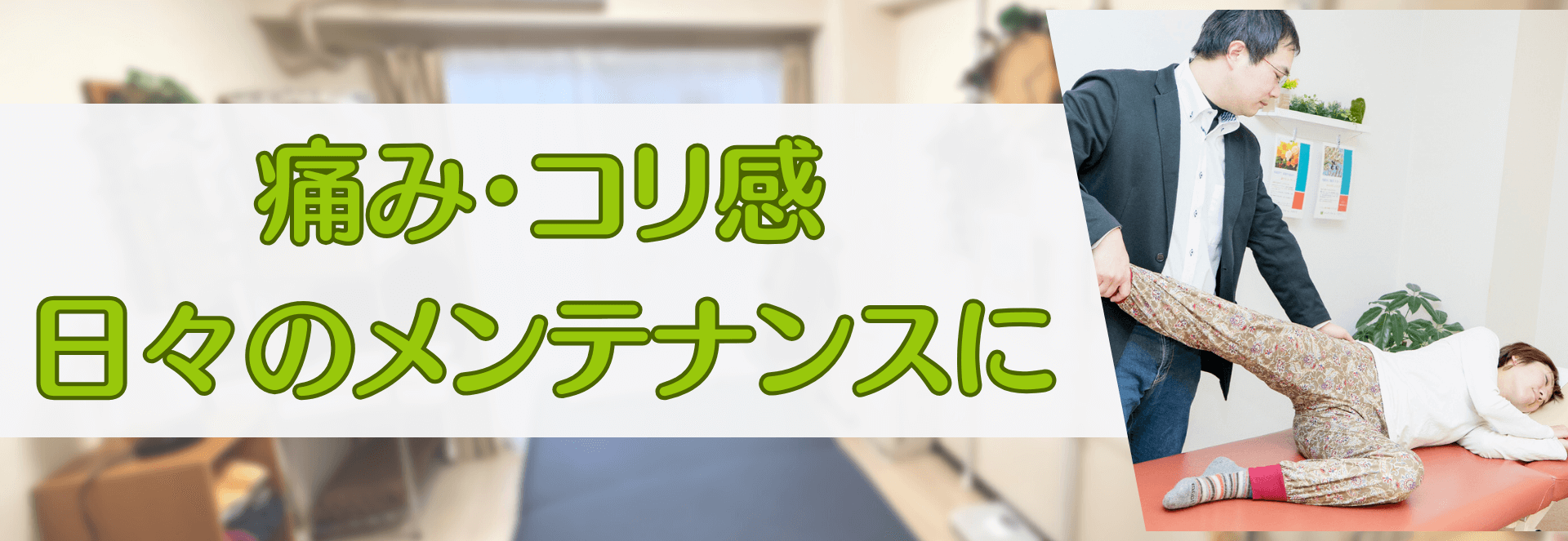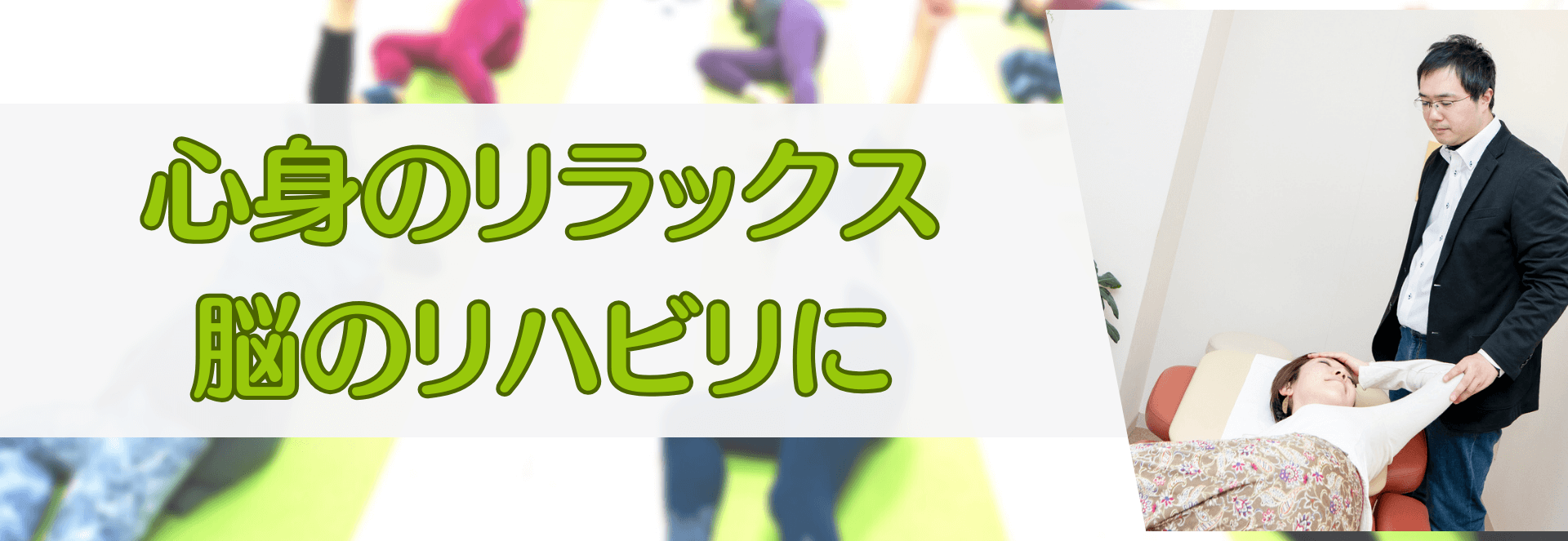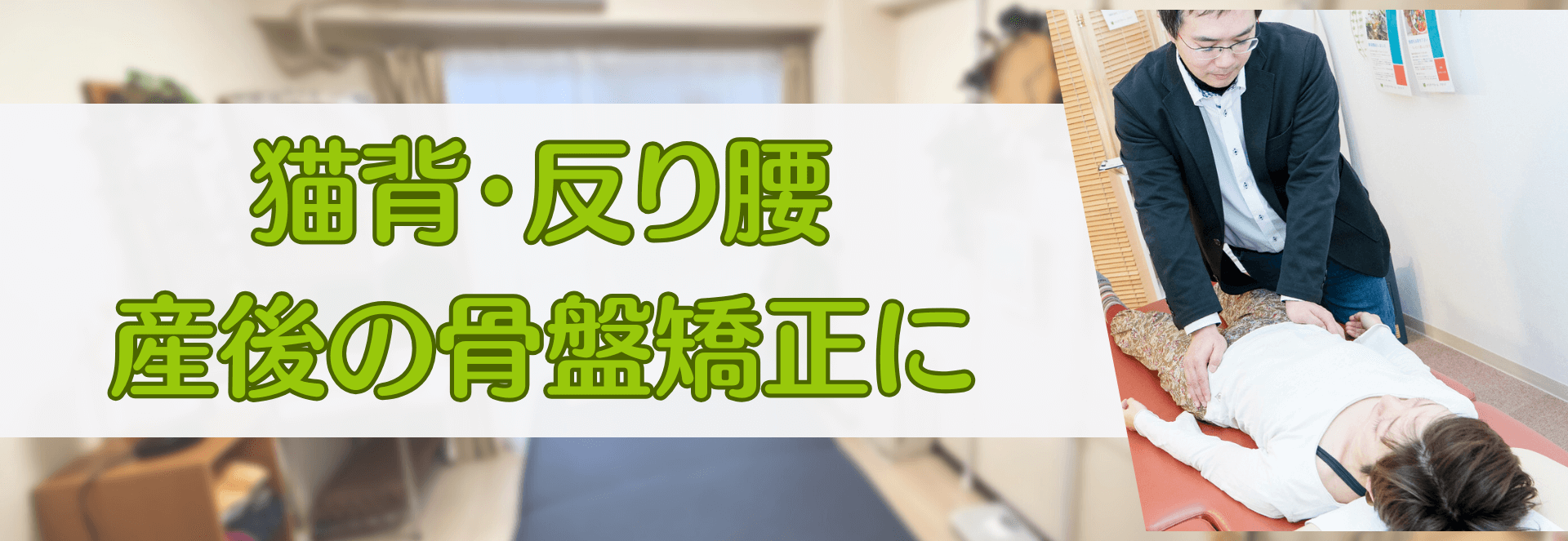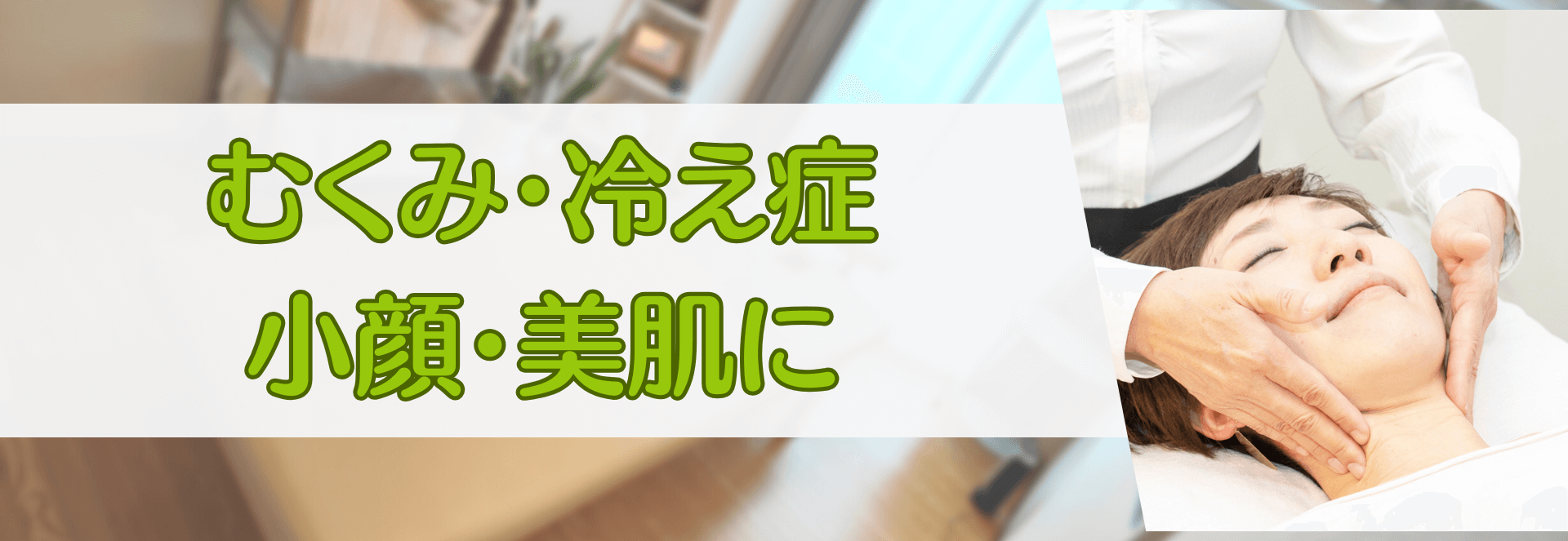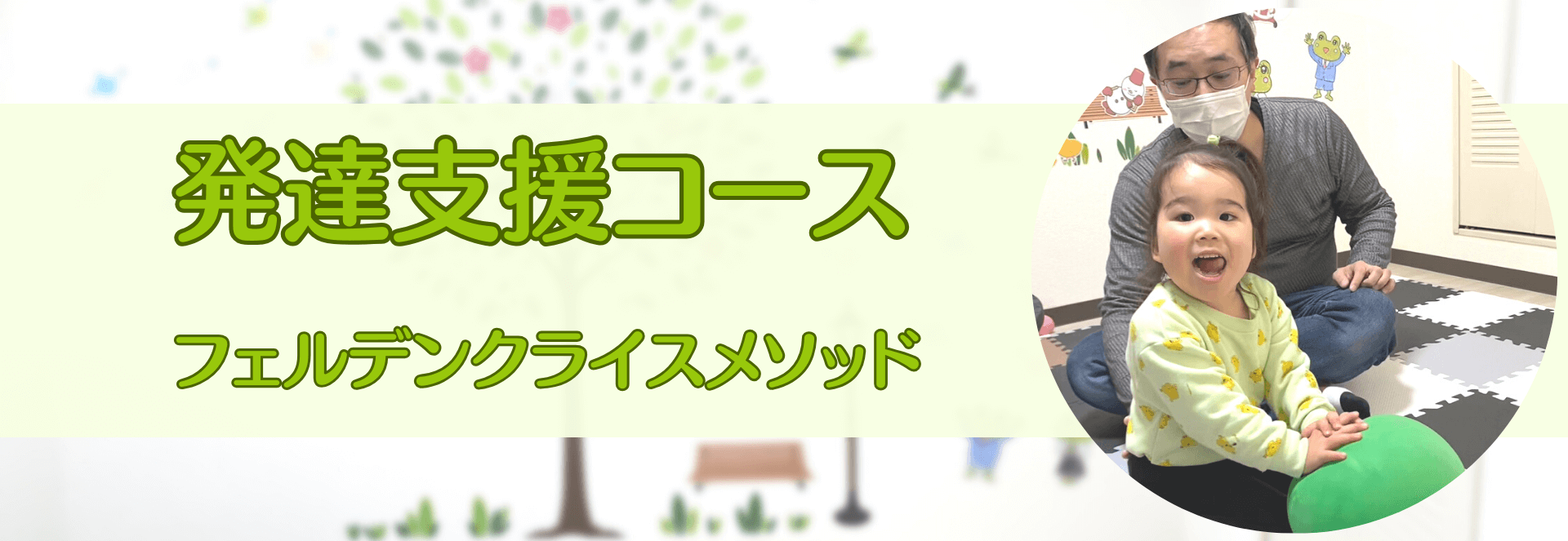こんにちは。国際公認フェルデンクライス講師、メディカルカイロプラクターの古淵かえる整体院院長の阿部です。
今回は、「箸の持ち方」と「発達」についてのお話です。
なんか、また水曜日のダウンタウンで、この話題が取り上げられたようですね。とんでもないアクセスが来たので、一時的に記事を下げてました。
~~~~
先日、ツイッターを見ていたら、「箸の持ち方」というのがトレンドに上がっていました。度々、「箸の持ち方」って、トレンドに上がるようなのですが、気になる人が多いのかも知れませんね。
箸の持ち方と言えば、真っ先に思い浮かんだのが桑マンこと、桑野信義さんです。
志村けんさんと一緒にコントをやってたという印象が強い方もいらっしゃるかと思いますが、元々はラッツ&スターでは、トランペットを担当していた方です。トランペットの腕は超一流なのですが、実は歌もとってもうまいんですよ。
今は色々な方の指摘によって、箸の持ち方は直されているようなのですが、以前はこんな箸の持ち方をしていました。

誰なんだ?(笑)
指が突っ張っていたりとか、薬指を器用に使う人も居ますけど、桑マンさんは以前はこんな感じでした。
たまにこんな持ち方の人いません?同級生でいました。
これ、しつけの問題だと思っていたんですけど、どうもそれだけじゃなさそうだなと、最近思うようになりました。
桑野信義さんの箸の持ち方を検証したテレビ番組(水曜日のダウンタウン)があるのですが、その番組の中で彼は父もトランぺッターで、同じような箸の持ち方をしていたと言っています。
これだけを聞くと、ただの「しつけ」の問題のような気がするのですが、生まれてからの発達の過程で、どこかすっ飛ばしているのではないかと思うのです。

この手の形、赤ちゃんのずり這いの時の手です。だいたい手と肘はこんな感じじゃないでしょうか?
手をグーに握ってることはあるでしょうけど、肘は外に張っているような感じですよね?
先程の箸の持ち方に似てませんか?
トランペットの持ち方にも共通していますよね?

おっさんのずり這い・・・(笑)
赤ちゃんのずり這いは、膝がおなかの横にまで上がってきて、同じ側の肘とひざが近づく動きで進みます。
この写真で言うと、右肘とわずかに曲がった右膝ですね。右側同士、左側同士と同じ側の身体を使います。ワニのような動きをするわけです。
ずり這いをしながら、腕の力を鍛え、体幹の筋を鍛え、そして、股関節を育てるのです。
そして、ずり這いの時期が終わったら、この後はハイハイをするようになるのですが、ハイハイをあまりしないで、いきなりつかまり立ちで立ちあがってしまう子が結構います。
おそらく、桑野信義さんは、このハイハイをすっ飛ばしてしまったのではないかと思っているのです。

ハイハイの手です。肘も閉じて折りたたみましたね。
肘がこの位置にあるから、自分の上半身をうつ伏せから高く持ち上げることが出来ます。

今度動かすのは、対側の手と脚です。クロスしてます。
右手と左脚を使えば、もう片方は支えとして使いますね。
こうやって左右交差する動きをすることによって、脳は交叉支配をするようになるのです。
右脳が左半身、左脳が右半身を支配するというように。この交叉支配が上手くいっていないと、右や左がわからなくなったりすることが見られます。
また、こうやってハイハイできるようになると、背骨に縦の上下の動きが入ってくるようになります。屈曲伸展の動きですね。
自分の中心となる軸が、より明確になってきます。自分の中心がわかるようになって、前後左右上下と、空間を認知できるようになります。交叉支配や空間認知の話はまた違う機会にします。ちょっと脱線してしまいました。

再び登場のこの写真・・・w
手首を固くして、肘も肩も柔らく動きそうには見えませんよね?
指先から肩甲骨まで、上肢帯が一体化して動いているような姿勢です。
ちっちゃい子がスプーンで食べているような姿勢ですね。
肘は外に張り、手のひらは常に下を向いた状態で食べています。
例えば、りんごをつかんで食べるという動きを行うには、手のひらをりんごに向けてつかんだら、口に持って行って食べるには、手のひらは自分の口に向けなければなりません。手首を返す動きが起こります。箸でものをつかんだら、手首を返して口に持ってきますでしょ?
この手首を返して、ものを食べる動きを、肘を広げたまま食べる場合と、肘を閉じながら食べる場合とで、どっちが楽に出来そうですか?
おそらく、肘を閉じた方が、肩も手首も緊張が少なく楽に出来ませんか?
肘を閉じた姿勢は、「ハイハイ」の姿勢に繋がります。
桑野信義さんは、肘を閉じる動きが不十分で、余計な力を上半身に入れながら過ごしてきたのではないかと考えています。つまり、このハイハイをする期間が短かったのではないかと思うところなのですね。
さらに、トランペットを持つ手を考えたら、手に対して、常に肘は開きますものね。
動画でもわかりますが、あれだけの腕前なので、若い頃からかなり練習をされてきたと思います。桑野さんの脳の中でのボディマップは、トランペットの握り方やずり這いに関する部分が大きくなっていて、箸を握る(手首を返す動き)マップは、相対的にかなり小さくなっていたのでしょうね。
ハイハイをあまりして来なかったことで、おそらく、上肢帯をひと固まりで動かすようになってしまい、彼の脳の中で上肢帯のボディマップが、うまく分化されないまま、トランペットでそれが強化されてしまい、箸をうまく握れなくなったのではないかと、私は考えています。
箸の持ち方は「しつけ」の問題ではなく、「運動発達」の問題かもしれない。
おとなの発達障害でお困りの方、お待ちしております。